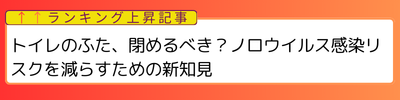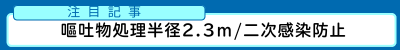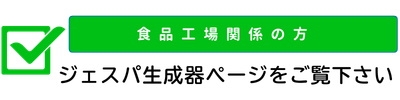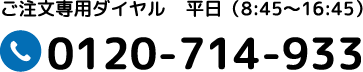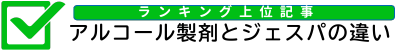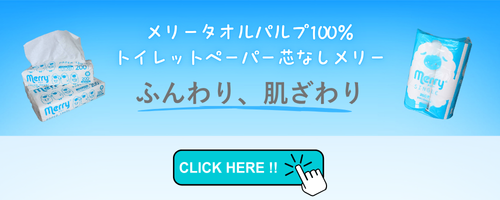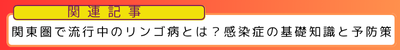ノロウイルス集団食中毒が全国で相次ぐ 高齢者施設・会食・委託調理で拡大、死亡例も
2月に入り、ノロウイルスによる集団食中毒が全国各地で相次いでいます。特に目立つのが、高齢者施設や医療・福祉施設での発生、そして会食や大人数利用施設での拡大です。一部では死亡例も報告されており、例年以上に注意が必要な状況となっています。
高齢者福祉施設での発生
福井県坂井市の高齢者福祉施設では、入居者35人からノロウイルスが検出され、食中毒と断定されました。患者間の感染は確認されていないとされています。
また、滋賀県内の介護施設では、いなり寿司などを食べた83人が発症し、2人が死亡。島根県内の高齢者施設でも集団食中毒が発生し、入所者のうち1人が死亡しています。群馬県でも高齢者施設利用者41人が発症するなど、各地で発生が確認されています。
高齢者は重症化リスクが高く、基礎疾患を有する方も多いため、施設内での感染拡大は深刻な影響を及ぼす可能性があります。
飲食店・会食施設でも相次ぐ発生
埼玉県熊谷市の飲食店では22人が発症し、営業停止処分となりました。長崎市のホテルでは新年会後に8人が食中毒症状を呈し、厨房が営業停止となっています。
さらに、栃木県足利市のゴルフ場レストランでは、670人の利用者のうち99人が発症する大規模な集団食中毒が発生しました。大人数への一括調理は、ひとたび汚染が起こると広範囲に影響が及ぶことを示しています。
産婦人科での発生事例
富山市では、産婦人科に入院中の妊産婦7人が提供された食事により食中毒症状を呈し、ノロウイルスが検出されました。医療機関や福祉施設など、免疫状態の変化しやすい方が利用する施設での発生も確認されています。
調理従事者を介した汚染リスクについて
今回の複数の事例では、調理従事者からノロウイルスが検出されたケースも報告されています。ノロウイルスによる食中毒は、食品そのものよりも「人を介した二次汚染」によって発生するケースが少なくありません。
ノロウイルスは非常に少ないウイルス量(10~100個程度)でも感染が成立するとされており、感染者の便や嘔吐物中には大量のウイルスが排出されます。調理従事者が感染していた場合、手指や器具を介して食品へウイルスが移行し、大規模な集団発生につながる可能性があります。
さらに重要なのは、ノロウイルスには不顕性感染(無症状感染)が存在する点です。明確な嘔吐や激しい下痢がなくても、軽度の軟便や腹部不快感のみで経過する場合があります。そのようなケースでも便中へのウイルス排出は起こり得るため、本人が体調不良と強く自覚していない状態で調理に従事してしまうリスクがあります。
大量調理施設や委託給食では、一人の体調不良が数十人から百人規模の発症につながる可能性があるため、軽微な消化器症状がある場合の就業制限、出勤前の体調確認の徹底、発症後の十分な休養期間の確保など、運用面での管理体制が極めて重要です。
流行期は「衛生管理範囲の拡張」が重要
今回のように高齢者施設や医療機関、会食施設などで発生が相次いでいる状況では、通常時と同じ衛生管理では不十分となる可能性があります。
流行期には、手指衛生の徹底に加え、トイレ個室内の便座・洗浄レバー・ドアノブ、トイレまでの導線部分(手すり・壁面・共用部)、共用テーブルや配膳カウンター周辺など、衛生管理の対象範囲を広げる視点が重要です。
ノロウイルスは環境中でも一定期間残存し、接触を介して感染が拡大する可能性があります。特に嘔吐物処理後の周辺環境やトイレ周辺は重点的な管理が求められます。
流行期には通常よりも清拭範囲を拡張し、適切な環境衛生対策を実施することが、施設内での拡大防止につながります。ジェスパのような環境衛生対策製品を活用しながら、日常管理の強化を図ることが重要です。

参考:関連報道
※リンク先は一定期間後、消失している場合がございます。
・福井県坂井市 高齢者福祉施設 食中毒
https://www.chunichi.co.jp/article/1202036
・埼玉 熊谷市 飲食店 ノロウイルス
https://news.yahoo.co.jp/articles/af5bb2d3a8ada3cbc9fa761757948c6cfd63158c
・長崎市 ホテル 新年会 食中毒
https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20260204-GYS1T00018/
・富山市 産婦人科 ノロウイルス
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/tut/2449143
・滋賀県 介護施設 集団食中毒
https://news.yahoo.co.jp/articles/71abbc9becdb152f2ce23490dc0aa338cbeaffba
・栃木県 足利市 ゴルフ場レストラン
https://www.tochigi-tv.jp/news2/page.php?id=295159
・島根県 高齢者施設 集団食中毒
https://news.yahoo.co.jp/articles/93d695e217a037ce4a66687eda9c0300292a172e
・群馬県 高齢者施設 食中毒
https://news.yahoo.co.jp/articles/f37741cfce3373024b519dfb4521e6030c0550b6